ゲーム音楽の制作から利用まで|著作権処理と契約トラブルの予防策を紹介
ゲーム開発において、ゲーム音楽は作品の世界観を支える重要な要素です。しかし、商用利用を前提とした制作では、著作権の理解と契約面での対応が欠かせません。
使用範囲や媒体ごとの制限、著作権の有効期間など、制作段階で確認すべき項目は多岐にわたります。適切な権利処理がなされていないと、公開後のトラブルや収益への影響につながる可能性もあります。
こちらでは、ゲーム音楽の制作と著作権に関する基本知識を整理し、商用利用における実務上のポイントを詳しく解説します。
BGM使用時に求められる著作権の基本知識
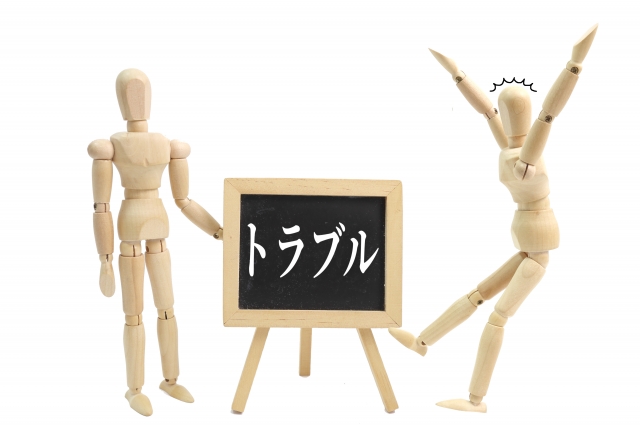
ゲーム制作においてBGMを取り入れる際は、まず著作権の基本的な考え方を理解しておく必要があります。著作権は、単なる形式的なルールではなく、音楽を安心して利用するための重要な法的枠組みです。特に商用作品の場合、誤った使用や契約の抜け漏れがあると、後から大きなトラブルにつながるおそれがあります。以下では、BGMを活用する際に押さえるべき著作権の基礎を解説します。
著作権とは
創作物を生み出した人が、その作品の使い方についてコントロールする権利です。音楽においては、主に作詞者、作曲者や編曲者などが著作権者に該当します。この権利には「無断で使われない権利」や「使用方法を制限できる権利」が含まれています。つまり、ゲームに音楽を使う場合、著作権者の許可がなければ利用できないのが原則です。
すべての音楽に自動的に発生する権利
著作権は、創作された瞬間に自動的に発生する権利であり、特別な申請や登録は不要です。例えば、ネットに公開された音楽素材や動画の一部を切り取って使う行為は、たとえ非営利であっても著作権侵害に該当する可能性があります。著作権者の許可が明示されていない限り、商用利用には十分な注意が求められます。
著作隣接権も関係する場合がある
音楽の利用には「著作権」だけでなく、「著作隣接権」という別の権利も関わることがあります。著作隣接権は、演奏者やレコード製作者、放送事業者などに与えられる権利です。例えば、市販CDの音源をゲームに組み込む場合、作曲者の著作権に加え、演奏者やレコード会社の権利もクリアしなければなりません。これらを見落とすと、ライセンス違反になる可能性があります。
二次利用や改変にも制限がある
BGMをそのまま使用するだけでなく「編集」「改変」「他の媒体への転用」などの二次利用を行う際にも、著作権の扱いに注意が必要です。例えば、ゲーム内で使った楽曲をプロモーション映像やSNS広告などに転用する場合、当初の契約内容によっては再契約や追加料金が発生することがあります。利用範囲をあらかじめ想定した契約設計が重要となります。
実際に発生しやすいトラブル例
ゲーム制作の現場では「フリー素材だと思って使っていた」「ライセンスの範囲を確認していなかった」「二次使用時の許可を取り忘れた」といった理由で、後から権利者との交渉やトラブルが発生するケースがあります。特に配信停止や賠償請求といったリスクは、商用タイトルにとって大きな損失につながります。使用前の権利チェックは必須といえます。
ゲーム音楽を商用利用する際に確認したいポイント
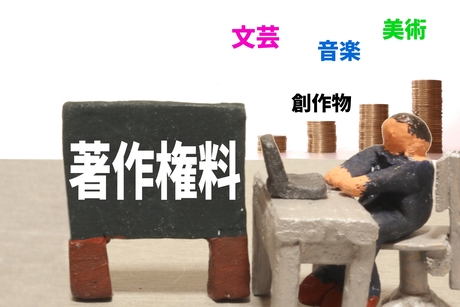
ゲームに使用するBGMが商用利用を前提とする場合、著作権に関する契約や取り決めが非常に重要です。無料公開されている音源であっても、利用条件やライセンスの範囲は制作物ごとに異なります。音楽の商用使用は、その楽曲が広告・収益と密接に関係するため、権利処理の不備は後々の事業展開に大きな影響を及ぼします。以下では、商用利用時に求められる具体的な著作権対応のポイントを整理します。
商用利用とは何を指すのか
著作権の実務上「商用利用」とは、コンテンツを用いて収益を得る目的で使用することを指します。例えば、有料アプリや課金機能のあるゲーム、広告付きの無料配信タイトルなどが該当します。音楽の商用利用では「どのような形で利益が発生するか」「どの程度の範囲で配信・公開されるか」がライセンス条件の判断基準となります。
利用契約では「使用範囲」と「使用媒体」を明確にする
著作権者と利用契約を結ぶ際は、単に「使ってもいいですか?」という曖昧なやり取りでは不十分です。ゲーム内での使用だけでなく、プロモーション用の動画、展示会でのデモプレイ、公式SNSでの発信など、多岐にわたる使用媒体が想定される場合、それらを事前に網羅して契約内容に盛り込む必要があります。契約書には「使用期間」「地域」「媒体」「改変の可否」「再委託の可否」などを記載し、トラブルを未然に防ぐことが求められます。
素材サイトの利用でも規約確認は必須
「フリーBGM」「商用可」と明記された音楽素材サイトでも、すべてのケースで自由に使えるとは限りません。一部の素材では「クレジット表記が必要」「編集は禁止」「法人利用は別契約が必要」といった細かい制限があります。また、サーバー負荷やアクセス集中によって素材が非公開になることもあり、ライセンスの永続性が保証されていない場合もあります。制作段階で素材を差し替えるリスクを避けるためにも、規約確認と必要に応じた事前相談は欠かせません。
YouTube・PVなど二次使用への対応
ゲーム内で使用するBGMを、そのままプロモーションビデオやSNS配信用素材として二次使用するケースも増えています。しかし、このような利用は「ゲーム本体での使用」とは別の使用とみなされることがあり、二次使用に対応したライセンスが必要になる場合があります。特にYouTubeでは自動検出システムにより、著作権者の許可なく使用された音源に対し、広告収益の差し止めや動画の削除措置が行われる可能性があります。
著作権フリーではなく、権利処理済みであることが重要
誤解されがちですが、「著作権フリー」という言葉は本来の法律用語ではありません。権利放棄されたものではなく、「使用料不要」や「制限が緩い」という意味で使われている場合が多く、実際には一定の条件下でのみ利用が許可されているものです。ゲーム音楽のように商用性が高く、複数媒体で展開される前提がある場合は、「著作権フリー」という言葉に惑わされず、権利関係を明確に処理したうえで使用することが求められます。
著作権の有効期間とその影響
ゲーム音楽の制作や利用においては、著作権の「期間」も見落とせない重要な要素です。著作権は無期限ではなく、一定の年数が経過すると効力が消滅します。特に長期的に配信・運営を行うゲームにおいては、著作権の保護期間や終了後の扱いについて事前に理解しておくことが不可欠です。以下では、著作権の有効期間と、それがゲームビジネスに与える影響について解説します。
著作権の保護期間は何年?
日本の著作権法においては、原則として著作権の保護期間は「著作者の死後70年」とされています。これは2018年の法改正により、それまでの50年から延長されたものです。共同著作物である場合は、最後に死亡した著作者を基準とします。また、法人が著作者となる「職務著作」の場合には、発行後または創作後70年が基準となります。
期間の起点に注意が必要
保護期間の起算点は著作物の種類や成立形態によって異なります。例えば、作曲者が個人の場合と法人の場合で起点が変わります。個人が作曲した楽曲は「作曲者の死後70年」ですが、株式会社などが権利を有するケースでは「公表後70年」になる場合もあります。使用する楽曲の権利者や契約形態に応じて、保護期間の解釈が変わるため注意が必要です。
保護期間の終了後は「パブリックドメイン」となる
著作権の保護期間が終了した楽曲は「パブリックドメイン」として誰でも自由に使用できる状態になります。BGMとして活用しやすい古典音楽(例:モーツァルト、バッハなど)は、このパブリックドメインに該当します。ただし、現代の演奏や録音には著作隣接権が発生するため、演奏データをそのまま使用する場合は別途の権利処理が必要になります。
「使用期間=安心」ではない理由
一度契約して使用許諾を得たとしても、楽曲の使用期間が著作権保護期間内である限り、再契約や更新が必要となるケースもあります。例えば、使用期間が「3年間」と定められた契約の場合、4年目以降の使用には追加契約が必要です。また、ゲーム自体が長期配信を前提としている場合、契約の更新忘れが原因で、音源の差し替えや一時的な配信停止に追い込まれるリスクもあります。
二次利用や移植時にも影響する
著作権期間の管理は、新規開発時だけでなく、移植やリメイク、シリーズ作品の再利用などでも重要です。過去に制作した音源を流用する際、当時の契約内容が不明確であれば、再度の契約確認や権利者との交渉が必要となります。特に古いプロジェクトでは、契約書が残っていないケースも多く、将来的なビジネス展開の障害になることがあります。
期間満了後でも信用性のある情報確認が重要
保護期間が満了していると判断した場合でも、正確な没年や公表年が確認できなければ、判断ミスにつながる可能性があります。著作権情報を取り扱う公的機関や信頼できるデータベースを参照し、事実に基づいた運用を行うことがリスク回避につながります。
BGMの著作権対策は専門家との連携が安心
ゲーム音楽の商用利用においては、著作権の理解と契約処理が非常に重要です。著作権の基本的な構造から商用での利用条件、さらには保護期間とその影響に至るまで、適切な知識と実務対応が求められます。特にプロモーションや二次利用、長期配信を視野に入れた開発を行う場合、最初の段階でリスクを想定した音楽制作を行うことが、後のトラブル回避につながります。
株式会社ブレインストームでは、ゲーム開発現場の要望やスケジュールに応じたオリジナルBGMの制作とあわせて、契約面でも安心して活用いただける形でのご提案が可能です。依頼に際して著作権に関するご不安やご相談があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
ゲーム音楽や音響制作に関するコラム
- 【ゲーム音楽制作】作曲上の注意点と音楽スタイルの選び方
- ゲーム音楽制作とリズムゲーム開発の基本|譜面データの設計ポイント
- 【ゲーム音楽制作】著作権の基礎知識|商用利用で見落とせない契約項目とは
- ゲームサウンド制作に役立つ効果音の知識|シンセや音素材の使い分けを解説
- 【BGM】ゲームサウンド制作の基本とは?魅力的なBGMを作るためのポイント
- ゲームサウンドの歴史と制作技術の進化|名作に学ぶ音楽表現のルーツとは
- ゲーム音楽の作り方入門|初心者でもできるループBGM制作の基本
- ゲーム音楽の作り方|制作に必要なソフト・MIDI・プラグインの基礎知識
- 音響制作会社が教える声優収録の進め方|キャスティングからゲーム向け整音
- 音響制作会社に依頼する前に!確認したい見積もりの要点と費用相場
ゲーム音楽の著作権管理のご相談なら株式会社ブレインストームへ
| 会社名 | 株式会社ブレインストーム |
|---|---|
| 所在地 | 〒186-0002 東京都国立市東1−8−2国立東壱番館201 |
| TEL | 042-571-8360 |
| 営業時間 | 平日 10:00-19:00 |
| 事業内容 |
|
| URL | https://www.nakataka.net |
